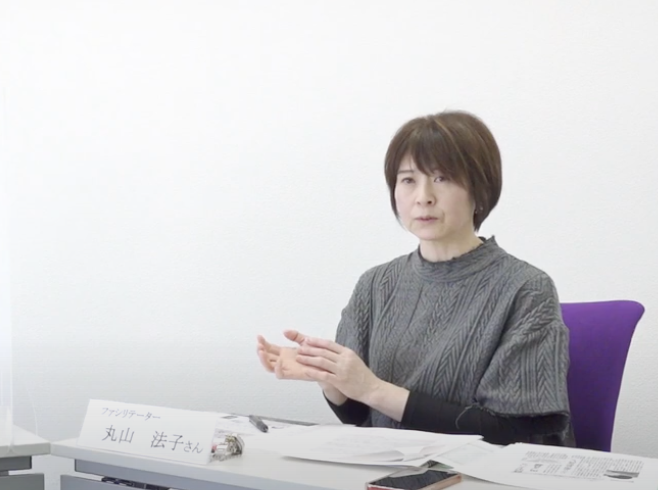ビジネスにいかすパーソナル・スキル
ビジネスの要であるコミュニケーション
信頼を築き、円滑な業務進行やチーム連携を実現する
再現性の高いトレーニング
部下をもったら「指導力」を磨こう
部下指導、育成に携わる方々にとって
コミュニケーションはとても重要です
- 目標共有とモチベーション向上: 効果的なコミュニケーションは、部下との明確な目標共有を実現し、彼らのモチベーションを高めます。適切なフィードバックと指導を通じて、個々の成長を支援し、チーム全体の成果を最大化します。
- 信頼構築と関係強化: オープンで透明性のあるコミュニケーションは、信頼関係を築く基盤です。部下との信頼の上に成り立つ関係は、意見交換やアイディア共有が活発になり、問題解決と創造性を促進します。
- スキル向上と自己成長: 適切なコミュニケーションは、部下のスキル向上と自己成長をサポートする手段です。フィードバックを通じて強化すべき点を示し、継続的な学習環境を提供することで、個人と組織のパフォーマンスを向上させます。
私たちは部下育成においてコミュニケーションスキルの重要性を深く理解し、豊富な経験と専門知識をもとに、あなたのリーダーシップを強化するお手伝いをいたします。
cöliaison standardの指導力研修
1 ティーチングとコーチングの使い分け研修
部下の成長度合いにあわせた指導方法を学び、成長を後押しします
2 うまく任せる上司になる研修
自分でやったほうが早いし確実!という思考から、部下へ手渡し成長を促進させます
3 気づいて変わるフィードバック研修
部下が受け取りやすい伝え方で、モチベーションを高めながら行動変容させます
4 すぐに使えるコーチングの基本研修
実用性の高いコーチングスキルを身につけて、信頼される上司になりましょう
5 世代の違いをこえる関わり方研修
年齢差のある部下との適切なコミュニケーションを学び、頼りになる上司になりましょう
その他、部下指導育成の問題にあわせた研修プログラムをご用意しています。まずはご相談ください。
ビジネスコミュニケーショントレーニング
こんなことはありませんか?
- 社員のモチベーションがまったりしている
- リーダーが育たない・なりたがらない
- 世代間でギスギスしている
- まじめに頑張っているのに生産性があがらない
- 言われたことはする。しかし言われないことはしない
- 雰囲気が悪く、採用しても続かない
- 「家庭の事情」ですぐに辞められてしまう
- なんとなく組織への愛着が薄い
- 頼りにしたい管理職が退職しそうでない人が残る・・・
職場風土が原因で起きている気がかりな日々
放置しておくと、コミュニケーションが低下して生産性まで下降します。
人材不足のうえ働き方改革で労働環境が大きく変化する現代は、
言い換えると人材開発に投資効果が高いともいわれています。
確実に組織の発展をめざせる社員教育の導入をご提案します。
1 マネジメントとリスク管理のこと
生産性のあがるリーダー仕事のすすめかたや考え方を学びたい
会議進行やプレゼンテーションをてきぱきとすすめたい
面談や相談、スーパービジョンの満足度をあげたい
2 部下育成とコミュニケーションのこと
部下育成に困らない「伝える」「聴く」「導く」力を身につけたい
ハラスメントを防ぐ「育てる」「叱る」「指導する」スキルを学びたい
スタッフや利用者の強みを引き出し可能性を育む視点と関わりを学びたい
ハラスメントにならないNOの言い方〜アサーティブコミュニケーション
3 ビジネスマインドとキャリアビジョンのこと
怒りやあきらめなど感情のコントロールができるようにしたい
ストレスで心身を大切にするためメンタルケアを考えたい
人生100年時代の働き方とキャリアビジョンを確認したい
4 全スタッフ対象に
信頼関係をつくる「伝える」「聞く」スキルを学びたい
迷いや不安でつぶれないための相談のしかたを身につけたい
組織理念や時代の流れを理解してキャリアビジョンをつくりたい
世代間コミュニケーションの風通しをよくしたい・・・
研修は ふたつと同じ内容であってはいけません
なぜなら、職場の問題と背景はそれぞれ違うからです
パッケージ研修は行いません
悩みも背景も、そして人もそれぞれ違います
私たちはゴールと課題にあわせて研修企画をつくります
◆リーダー研修
後輩や部下をもち、将来の管理職を期待するリーダー社員を対象に
・人材マネジメント
・業務マネジメント
・セルフマネジメント
業務に求められるテクニックと考え方をお伝えしてスキル向上をめざす研修プログラムです
成果イメージ
・部下の指導、教育力が身につき、育成に強くなる
・しっかり休み、しっかり働くという職場環境を整え、生産性が向上する
・ミスや事故を防ぎ、ケアの質を向上する視点をもつ
・リーダー自身の思考と習慣を改善し、成長意欲を高める
◆社員研修
新任社員を含めた全社員を対象に
メンタルヘルスと感情マネジメント
タイムマネジメントと優先順位設定
ビジネスマインドとキャリアデザイン
相互理解とハラスメント対策
幸福度の高い職場環境を整える研修プログラムです
成果イメージ
・人に関心をもち、もっともっと!と働く意欲を高める
・自分の適性や強みを知り、コミュニケーションスキルを身につける
・キャリアを描き、具体的な行動目標を設定する
・お互いの対話によって、職場や事業所への帰属意識を高める
経営者様、人事担当者様の気掛かりを解決するために少しでもお力になりたいと考えてきました。
原因の解明や研修でできることなど、ご相談をしながら企画を一緒に作るところから始めます。
せっかくの研修を有効に活用するために、打合せをていねいに行います。
Zoomやお電話、メールで無料でご相談対応をしています。
お問い合わせページからお申し込みください。
話し合いの進行役 コーディネーター・ファシリテーター
人々の活動ができるよう支援し、うまくことが運ぶよう舵取りするというファシリテーションは、問題解決、アイデア創造、教育、学習など、あらゆる知識創造活動を支援し促進していく働きです。
その役割を担う人がファシリテーター。司会進行とも言われます。
あくまで中立な立場からプロセスに貢献し、スムーズにゴールをめざします。
- 司会進行
合意形成をめざして、たとえば、決まらない・ 決まったことが進まない・感情的になって紛糾する・誰も発言しないなど、決まらない会議を解決し、より多くの意見 を引き出し、まとめ、話の流れを交通整理します。 - シンポジウムやパネルディスカッションのコーディネーター
テーマの理解を深めるために、登壇者の意見を相互に共通点や相違点を整理しながらライブ感あふれる双方向の対話を生み出し、聴き手である参加者にとって理解しやすい結論と納得へ導きます。 - ワークショップ・ファシリテーター
チームミーティングや研修など、共通するテーマに集まった人々が話し合いのなかで、目標や課題、 現状の確認と共通理解、アイデア創出やヒントを発見するなど、ワークショップのデザインと運営を行います。 - 実績
「認知症になっても困らない地域に!認知症フォーラム」朝日新聞厚生文化事業団・府中町
「人生計画をつくろう」広島県医師会・広島県地域医療機構
「これからの地域包括ケア人材のゆくえ」 地域包括ケア実践研究会 ほか